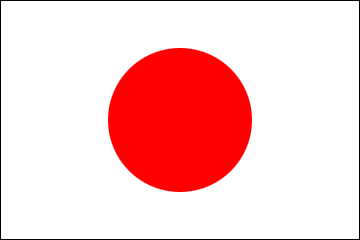二国間関係
平成27年10月5日
1- 二国間関係
-
1. 政治関係
- 1990年5月22日の南北イエメン統一に伴い、同23日、日本はイエメン共和国を承認しました。同25日、日本とイエメンは外交関係を開設しています。なお、統一以前は、旧南北イエメンそれぞれを国家承認し、外交関係を有していました。
- 1990年7月にアデン出張駐在官事務所を開設しましたが、1997年12月に閉鎖されています。
- 1990年11月、イエメン・日本友好協会が設立されました(現在は活動を休止しています)。
- 2011年3月、現地治安情勢の悪化を受け、サヌアの日本大使館を一時閉館(アラブ首長国連邦のアブダビでイエメン関係業務を継続)、同年12月、日本大使館を再開しました。
- 2015年2月、現地治安情勢の悪化を受け、サヌアの日本大使館を一時閉館し、同年5月よりサウジアラビアのリヤド(在サウジアラビア日本国大使館内)にてイエメン関係業務を継続しています。
- 2017年9月、日アラブ政治対話において、4年ぶりとなる日イエメン外相会談を開催しました。また同月、ニューヨークにおけるイエメン人道状況会合で日本がイエメンの停戦や復興に向けて継続的に関与していくことを表明しました。
- 2022年5月、緊急の人道ニーズに対応するとともに停戦合意を支えるため、イエメンに対するWFPを通じた1,000万ドルの緊急人道支援の供与を決定しました。小田原副大臣(当時)は、ニューヨークにおいて、ビン・ムバーラク外相(当時)と会談し、今後も、国連や関係国と連携しつつ、イエメンにおける平和と安定の実現に積極的に取り組んでいく旨表明しました。
- 2022年12月、武井副大臣(当時)は、ローマにおいてビン・ムバーラク外相(当時)と会談し、10月に失効した停戦合意の延長に向けたイエメン正統政府の努力を評価するとともに、日本は、イエメン正統政府と引き続き連携しながら、イエメンにおける恒久的和平の実現に向けた取組を継続していく旨表明しました。
- 2023年5月、グランドバーグ国連事務総長イエメン担当特使の訪日に際し、高木大臣政務官(当時)が同特使と会談し、イエメンにおける平和と安定の実現に向け、日本と国連がより一層緊密に連携していくことを確認しました。
- 2024年6月、日イエメン友好議連(会長:西銘恒三郎議員)が設立されました。
-
2. 経済関係
対日貿易
- 貿易額(2023年/財務省貿易統計)
対日輸出 8.91億円
対日輸入 345.9億円 - 主要品目
対日輸出 植物性油脂、コーヒー豆、魚介類(えび等)
対日輸入 機械類、自動車
- 貿易額(2023年/財務省貿易統計)
-
3. 文化関係
- 2005年、我が国はサヌアにて伝統能の公演、空手デモンストレーション、日本映画上映会を実施しました。同年、イエメンは愛知県で開催された愛・地球博に参加しています。また、2006年、我が国は生け花デモンストレーション、手仕事のかたち展、日本映画週間を実施しました。さらに2007年から2011年は日本の文化を1週間集中して紹介する「日本文化週間」を実施し、毎回好評を得ました。
-
4. 要人往来
(1)往訪(1974年以降) 年月 要人名 1974年1月 小坂善太郎特使 1975年8月 羽田野忠文外務政務次官 1983年7月 石川要三外務政務次官 1985年7月 左藤恵郵政大臣 1987年9月 江藤隆美特使(革命25周年記念) 2000年5月 小沢辰夫特使(統一10周年記念) 2000年9月 福田康夫日・イエメン友好協会会長(当時) 2001年8月 丸谷佳織外務大臣政務官 2002年9月 杉浦正健外務副大臣 2005年3月 河井克行外務大臣政務官 2006年7月 伊藤信太郎外務大臣政務官 2008年6月 宇野治外務大臣政務官 2009年12月 尾辻秀久元厚生労働大臣 2014年1月 牧野たかお外務大臣政務官 (2)来訪(1987年以降、主要なもののみ) 年月 要人名 1987年10月 イリヤーニ副首相兼外相(外務省賓客) 1990年11月 アブドルガニー大統領評議会メンバー(即位の礼) 1993年11月 イリヤーニ計画・開発相(外務省賓客) 1996年12月 イリヤーニ副首相兼外相(外務省賓客) 1997年11月 シュアイビー教育相(世銀招聘) 1998年2月 フセイン水産資源相 1998年5月 ワジーフ石油鉱物資源相 1999年3月 サーレハ大統領(公式実務訪問) 1999年8月 ワジーフ石油鉱物資源相 2001年11月 アハマディー漁業資源相 2002年1月 スーファーン計画開発相 2002年3月 カルビー外相(外務省賓客) 2004年3月 イリヤーニ水・環境相 2005年2月 アルシャリーフ最高選挙委員長(外務省招聘) 2005年11月 サーレハ大統領(実務訪問賓客) 2007年8月 ウバード青年・スポーツ相 2008年3月 バハーハ石油鉱物資源相 2008年4月 アルハビー副首相(経済担当)兼計画・国際協力相 2008年6月 アクワ外務次官補(外務省招待) 2009年2月 アッタール投資庁長官(外務省招待) 2009年11月 ラーシウ沿岸警備隊長官(外務省招待) 2009年12月 ムタワッキル産業・貿易相(日・アラブ経済フォーラム出席) 2010年10月 ムジャッワル首相(COP10出席) 2010年10月 イリヤーニ水・環境相(COP10出席) 2010年11月 カルビー外相(外務省賓客) 2010年12月 ハイド内務省作戦局長(外務省招待) 2012年10月 アッ・サアディ計画・国際協力相(外務省閣僚級招へい) 2012年10月 ワジーフ財務相(IMF・世銀総会出席) 2013年9月 サッラーム観光相(旅博出席) 2013年10月 ハーリド水・環境相(水銀に関する水俣条約外交会議出席) 2013年12月 カルビー外相(外務省賓客) 2013年12月 ムフセン投資庁長官(日アラブ経済フォーラム出席) 2014年9月 カルマン「束縛のない女性ジャーナリスト」代表(女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム出席) 2015年8月 サッカーフ情報相(女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム出席) 2020年2月 ムハンマド・タービト公共事業・道路副大臣(JICAによる招聘) 2023年2月 バースハイブ計画国際協力副大臣(JICA本邦研修への参加) -
5. 二国間条約・取極
- 1989年9月9日 青年海外協力隊派遣取極締結
- 1993年7月29日 青年海外協力隊派遣取極の改定
- 1993年11月9日 技術協力協定の締結
-
6. 外交使節
- アーデル・アリー・アハマド・アル=スナイニー 駐日特命全権大使